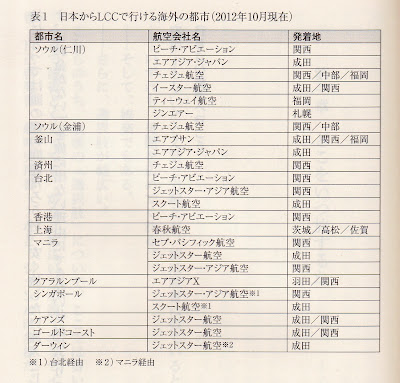今回は、猫について私がいつも感じていることを詠んでみた。
(1) 正体もなく眠りいる家猫は知らざる恋の夢を見るらん
最近は猫を放し飼いにするのは、「非常識」との認識が広がっているようであるが、一昔前は、犬はつないで飼うが猫は放し飼いで飼うのが普通であった。50年前、私が大学に入るまで住んでいた家でも犬と猫をずっと飼っていたが、犬は庭につながれていたが、猫は自由に家の内外を気ままに歩き回り、多分自分の縄張りを持っていたのであろうが、トカゲなど変なものを家に持ち込んだり、外でけんかもするし、二、三日帰ってこないこともよくあった。猫は自由な生き物であって束縛を嫌うので、そうするものだ、そうしなければならないものだと私はつい最近まで信じていたのであるが、どうもそうではないらしい。家の中で自由に走り回らせておけば、それで十分でありかえって外なんかには出さないほうがいいらしい。外に出すと、他の猫とのトラブルでけがをしたり変な病気をもらってきたり、また交通事故にあったりとなかなか大変らしい。そういうことで、最近の家猫は去勢をして、一生家の中で飼うのが常識らしい。そうなってくると、春の風物詩でもあり、春の季語にもなっている「猫の恋」も見られなくなる。猫も「生き物」であるから、当然発情期もあるはずであるが、それを人為的に奪って家の中に閉じ込めて、人間のいわゆるペットとしてだけの生き物にしてしまうのは、人間の傲慢さが垣間見えて可愛そうな気がする。私の長年の夢は、人家もほとんどない雑木林の中に一軒家を立てて、放し飼いの猫と暮らすことであるが、今となっては贅沢な望みのようだ。
(2) 悠然と前を横切る野良猫にその前世を聞きてみたしも
(3) そこまでも身構えずとも良かりしに猫は半身にわれをにらめり
猫が日向ぼっこを見るのを見かけると、私はときどき手招きをして呼びよせようとする。10匹のうち1っ匹ぐらいは寄ってくるが、残りの三分の一は逃げ去り、三分の一は無視、三分の一は上記のように半身になって身構える。猫にもいろいろの性格があるようだ。
2013.1.30
Yukikaze